「その子らしさ」を愛おしく思えるようになるまで⑥ 〜「尊重すべき一つの特性」〜
- えがおのたね
- 2025年9月15日
- 読了時間: 3分
幼少期の息子は、衣服や排せつなど様々なこだわりがありました。
そして、自分の思い通りにならないと、パニックになる…。
そんな、生きづらさを抱えていました。
彼のことを少しでも理解したくて、発達のドクターや心理の先生のもとへ通いました。
(息子をASD(自閉スペクトラム症)と診断したW先生は、10年以上たった今でもお世話になっています。)
私は先生に、靴や服、排泄のこだわりで困っていることを伝えました。
先生は、
「壊れた靴も、紙パンツも本人にとっては必要なものなんだよね。
でもそれで困るようなら、親の思いを伝えていくのも大事かもしれないね。」
とアドバイスしてくれました。
そしてこんなことも…。
診察中、先生の机に電卓があるのを見つけた息子。
すばやく手に取ると、ひたすら、
「123456789」
と、「数字を打っては消す」を繰り返し始めました。
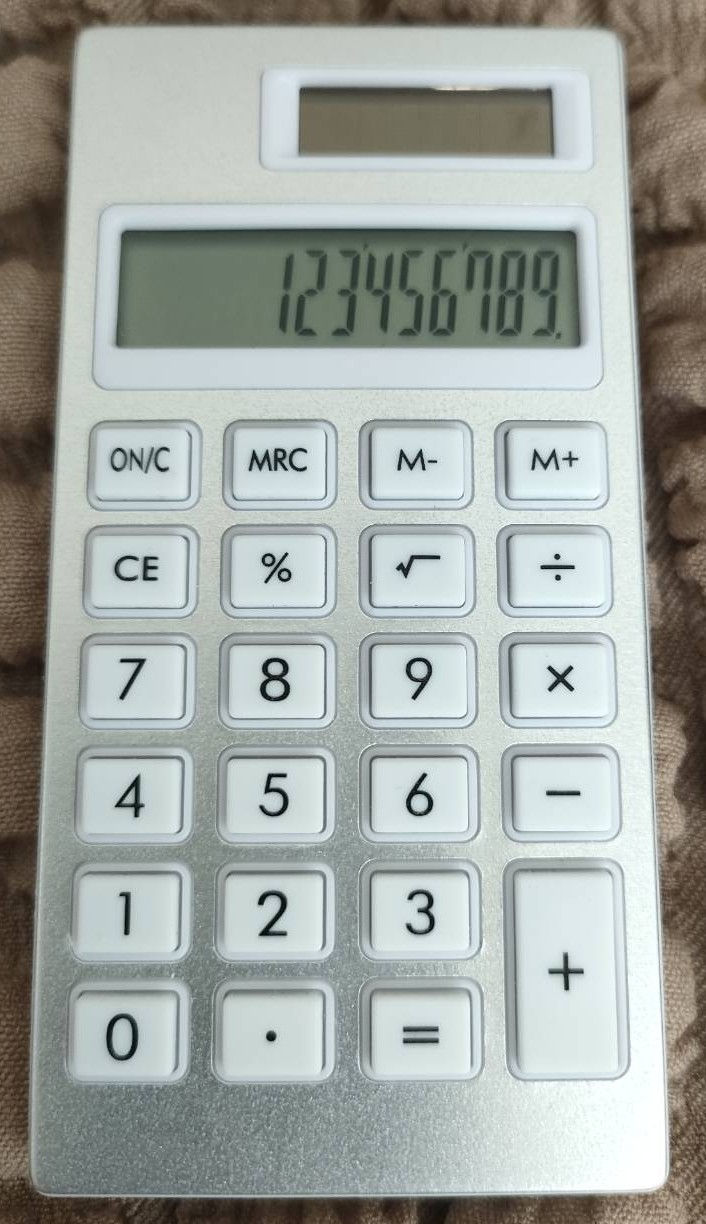
先生はそれを見て、
「自分が押した数字が出るのが楽しいんだね。そこにある種の『美』も感じているんだろうね。」
と言いました。そして、
「ASDの人は、私たちとは異なる感性を持っている。その『違い』を楽しめるようになるといいね。」
と教えてくれました。
また、3歳ごろには、心理の先生とこんな会話がありました。
私:うちの子、ドアやエレベーターの方にばかり行って、お友達に全然興味をもたないんですよ。
先:そうですか…。
実はこの前、ADHD(注意欠如・多動症)の子のお母さんが、
「うちの子、落ち着きがなくって。」
と、言われて。私は、
「『まあ、特性ですからね…。』ってお伝えしたんですけど…。」
それを聞いて私は、
「『変わるもの』と『変わらないもの』がある。」
ということに改めて気づかされました。
W先生も心理の先生も、それからもずっと、
親の「なんとかしなくては…。」という思いには寄り添いながら、
「自閉症は、『なんとかしなくてはいけない問題』ではなく、『尊重すべき一つの特性である』」
という事を、教え続けてくれました。
先生方の言葉を聞いて私は、
「自閉症についてもっと知りたい」
と思い、本やセミナー、動画などで学び始めました。
それから心理の先生のもとで、発達テストも受けました。
息子は、ワーキングメモリー(情報を一時的に記憶しながら処理する能力)は「平均〜平均以上」。
それに対し、言語理解(言語を使って概念を理解し、それを他の人に説明する能力)が「非常に低い〜低い」という結果でした。
私はそこではじめて、
「言葉での理解が難しい彼が、周囲で起きていることの意味が理解できず、物事の見通しも立てづらいこと。
それゆえ、自分の記憶を頼りに、『以前と同じ』ことを心の支えに毎日を過ごしている。」
ということに気づきました。
「以前と『同じ』にこだわる。違うとパニックになる。」
そんな息子の行動の理由が分かると、少しずつその気持ちに寄り添えるようになりました。
そして、そのように理解が深まると、「なぜ分からないのだろう?」と、息子に対して思うのではなく、
「どのようにしたら伝わるのだろう?」と、こちら側の問題としてとらえられるようになりました。
私が、「わが子らしさ」を愛おしく思えるようになった理由の一つは、
「その子自身への理解が深まったこと」が大きいと感じています。
次回は、もう一つの理由についてお伝え出来たら。と思います。

コメント